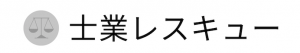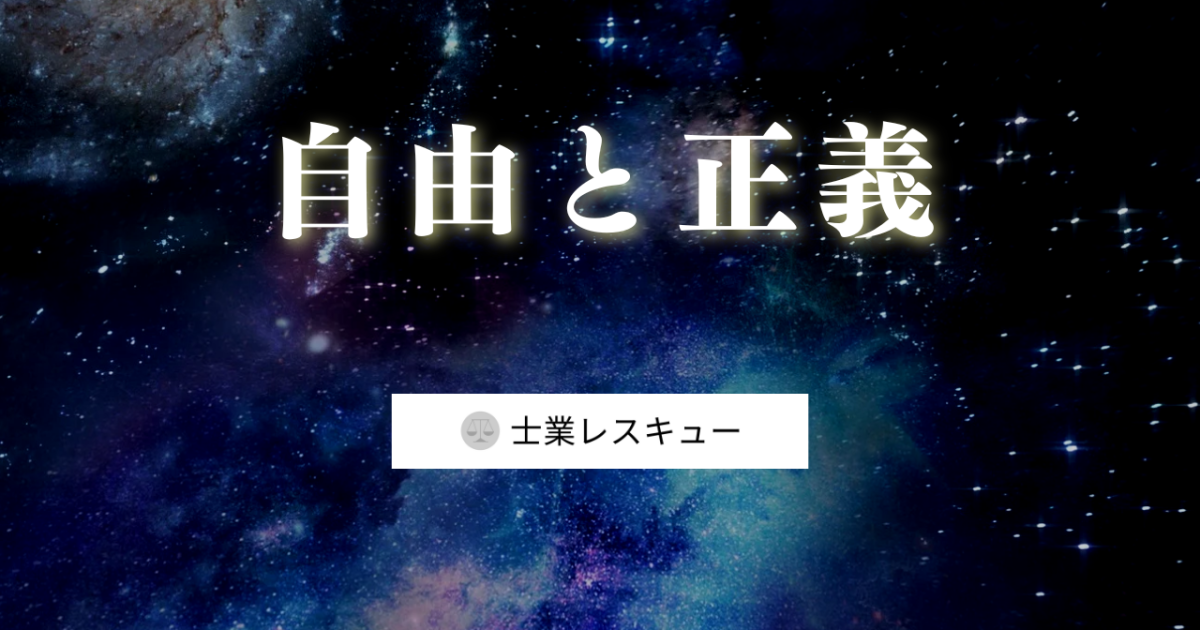コンテンツ
自由と正義2025年8月号
今月号は、
単位会の懲戒9件
| 戒告 | 4件 |
| 業務停止1月 | 2件 |
| 業務停止3月 | 1件 |
| 業務停止6月 | 1件 |
| 業務停止1年 | 1件 |
日弁連の審査請求(棄却 4件、処分変更(3月→2月)1件)でした。
単位会の懲戒
東京弁護士会 業務停止3月
(1)被懲戒者は、2021年7月20日、Aから受任していないにもかかわらず、懲戒請求者に対し、Aの代理人として保険金を請求する旨の受任通知を送付した。また、被懲戒者は、受任通知発送後、Aからの電話連絡により、委任していない旨を直接聞かされたにもかかわらず、懲戒請求者に対してその旨は誤りである旨の連絡をしていないどころか、むしろ、同年11月22日、Aに対し、和解金の金額を記載し及び保険会社Bに対して保険金請求を交渉内容等を報告したとの書面を交付した。
(2)被懲戒者は、弁護士法第72条の規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のあるにもかかわらず、2021年4月頃から同年12月頃にかけて、保険金請求をしようとする保険契約者の案件につき、計40件程度の紹介を受けた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第41条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
非弁提携が疑われる事案であると思われます。なお、この弁護士に関しては逮捕報道もされているようです。
東京弁護士会 業務停止1月
被懲戒者は、職務上請求の要件を満たさないにもかかわらず、調査会社である株式会社Aから懲戒請求者の住所調査の依頼を受け、事実と異なる利用目的や依頼者名を記載して、2021年7月16日、職務上請求を行い、懲戒請求者の実父の改製原戸籍謄本2通を取得し、同月27日、職務上請求を行い、懲戒請求者の戸籍謄本、改製原戸籍謄本及び戸籍の附票を取得し、同年8月頃、懲戒請求者の住所票及び戸籍の附票の写し等の職務上請求文書をAに取得した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
職務上請求の不正使用事案です。
東京弁護士会 業務停止6月
(1)被懲戒者は、2023年1月頃から同年10月頃までの間、懲戒請求者Aら8名との間で詐欺被害の被害金の回収に関する委任契約を締結するに際し、懲戒請求者らからの事情聴取、事件経過の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用等の説明を自己または直接行わず、もっぱら被懲戒者の法律事務所の事務職員に行わせた上、懲戒請求者Aらへの対応を適切に行うべきところ、事務職員に対応させたまま放置し、適切な連絡及び説明を怠った。
(2)被懲戒者は、2023年3月頃、いわゆる国際ロマンス詐欺などのメール、電話、SNS等のやりとりで行われた非接触型の詐欺であっても、被懲戒者に依頼をすれば一般的な弁護士に依頼するよりも多くの被害回復を得られるかのような、事実に合致せず、誤導又は誤認のおそれがあり、誇大又は過度な期待を抱かせる内容を含む広告を作成し、インターネット上で公開していた。
(3)被懲戒者は、2023年3月18日、懲戒請求者Aとの間で詐欺被害の被害金の回復に関する委任契約を締結するに際して、被害金について十分な回収が得られる可能性が低かったにもかかわらず、そのような事件処理の見通しの説明をしなかった。
(4)被懲戒者は、2023年9月14日以降、所属弁護士会の非弁提携弁護士対策本部から被懲戒者の法律事務所の事務職員との雇用契約書や業務委託契約書等の資料の提出を複数回にわたって求められたにもかかわらず、正当な理由もなく提出に応じなかった。
(5)被懲戒者は、2024年3月14日、懲戒請求者Bに対して、一般的には被害金等の回収が困難であり、弁護士に支払った金額以上の成果が得られない可能性があることの説明をしていないにもかかわらず、所属弁護士会に提出する報告書において、上記説明を受けたとの項目にチェックするよう事実と異なる記載をすることを求めた。
(6)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
こちらも非弁提携事案です。東京弁護士会が一斉に調査を行ったことがきっかけかもしれません。
大阪弁護士会 戒告
被懲戒者は、2023年12月24日から2024年1月6日頃にかけて、被懲戒者の運営するアカウントを用いたSNSサービスにおいて、「人の善意を利用して私服をこやす最低のビジネスモデル」等と懲戒請求者である特定非営利活動法人A及び法人の創設者であるBを誹謗中傷する侮辱的な投稿をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
某SNSで話題になっていました。人口に膾炙していますが、SNSは弁護士といえども感情的になりやすい上、客観的に発言内容が残ってしまうメディアです。不適切な投稿をしてしまった後、適切な対応を取ることができるかが問われます。
東京弁護士会 戒告
東京弁護士会 戒告
基本的に同一事案ですので、まとめて引用します。
(1)被懲戒者は、A弁護士と中心となって、懲戒請求者B株式会社らを被告とする損害賠償請求訴訟を他の弁護士らとともに共同受任したところ、上記訴訟に関する記者会見を開催することとし、上記記者会見において懲戒請求者B社らの社会的評価を低下することをA弁護士らと相互に認識した上で、2018年10月11日に、他の弁護士らとともに、A弁護士が司会を務める記者会見を開催し、懲戒請求者B社らの名誉を毀損する内容の発言をした。また、被懲戒者は、同日、自身及びA弁護士らが共同代表理事を務めるC協会並びに自身が代表理事である一般社団法人Dのウェブサイト上において懲戒請求者B社らの名誉を棄損する内容の記事を掲載した。
(2)被懲戒者は、2018年10月26日、懲戒請求者B社の代表者の名誉を毀損する内容のツイートを投稿した。
(3)被懲戒者は、A弁護士とともに、上記(1)の訴訟に関し、2019年8月から9月にかけて、Eらと面会して事情を聴取したところ、その後作成した陳述書への署名及び捺印をためらうEに対し、利益を供与することを示唆して陳述書への署名及び捺印を求めた。
(4)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
メディアでも取り上げられた事案です。訴訟提起時点における記者会見は、その性質上どうしても名誉棄損を内包するものであって、違法性阻却事由の慎重な検討が求められます。また、訴訟が進行するに当たって、当初の目論見と異なる展開になることが予想されたときの対応にも一石を投じる意味があるかもしれません。
愛知県弁護士会 業務停止1月
(1)被懲戒者は、2018年7月頃、懲戒請求者から、夫婦関係調整調停申立事件、預金債権の仮差押申立事件等を受任したが、これらの事件の受任に当たり委任契約書を作成せず、同年11月懲戒請求者から委任されて提起した離婚訴訟についても委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者から事件を受任するに当たり、弁護士費用に関する明確な説明を行わず、懲戒請求者被懲戒者を解任する旨通知した2019年6月18日以降、支払った弁護士報酬の説明を再三求めたにもかかわらず、領収証のただし書に記載しているとおりである等と回答するのみで、懲戒請求者に改めて説明することを理由なく拒否し続けた。
(2) 被懲戒者は、2019年2月、懲戒請求者が作成した文書の余白に、二度にわたり「バカ」と自らの依頼者を罵り侮辱する記載をして返信し、同年4月19日、「貴方には文才がない」と懲戒請求者を揶揄するような表現をわざわざ記載した文書を懲戒請求者にファクシミリで送信した。また、被懲戒者は、同年6月18日、懲戒請求者より解任を告げられ、弁護士費用である着手金に該当する分の明細を明確にした上で返金してほしいと求められたのに対し、委任契約上返還すべき着手金があるかどうかを検討し、その説明をする必要があったにもかかわらず、その説明をすることなく、懲戒請求者を被告として民事訴訟を起こす旨を記載した文書を懲戒請求者にファクシミリで送信し、同月28日、「お金に汚い性格」「本当にエゲツナイ人」と懲戒請求者を罵り、侮辱、非難した表現を記載した文書を懲戒請求者にファクシミリで送信した。
(3) 被懲戒者は、上記(1)の仮差押申立事件について、裁判所の決定に基づき、2018年8月9日に320万円、同月10日に10万円の計330万円の供託金をそれぞれ第三者供託の方式で立て替えて供託し、同月31日に懲戒請求者が上記供託金相当額330万円を被懲戒者に支払ったところ、供託金取戻請求権は第三者供託とした被懲戒者に帰属し、被懲戒者において供託金を取り戻し、これを懲戒請求者に対して返還する義務を負い、自らその義務を負うことを知り、それを履行することが可能であったにもかかわらず、上記(1)の離婚訴訟の顛末の報告、被懲戒者の謝罪を条件とすることに固執し、懲戒請求者がA弁護士らに委任して提起した上記供託金相当額等の支払を求める損害賠償請求訴訟の2021年12月10日の期日まで、不当に履行を拒否し続けた。
(4) 被懲戒者は、上記(3)の供託金取戻請求権の債権譲渡の方法への協力を依頼した懲戒請求者に対し、2020年3月23日、これを拒否し、法律上の根拠等を含めて懲戒請求者及び同人が依頼した弁護士から直接文書にて誠実に返事をもらいたい旨を要求し、同月26日、これを受けたA弁護士らから懲戒請求者の代理人であることが明示された供託金の取戻手続に関する説明書面を送付されて回答を得たにもかかわらず、同年4月1日、あえてA弁護士らを介さず、懲戒請求者を非難し、被懲戒者へのお詫びが前提である等の交渉の条件を付した内容証明郵便の文書を、直接懲戒請求者に送付し、懲戒請求者が上記(3)の損害賠償請求訴訟を提起した後の2021年10月になってもなお、A弁護士らの対応を正当な理由なく非難する内容の文書を直接懲戒請求者に送付した。(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第29条第1項及び第30条第1項に、上記(2)の行為は同規程第6条に、上記(3)の行為は同規程第5条、第6条及び第45条に、上記(4)の行為は同規程第52条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
非常にボリュームのある懲戒事由です。ここに記載されている事実関係を前提にすると、むしろこの内容でこの量定で済んだ理由が気になります。
第二東京弁護士会 戒告
被懲戒者は、2000年9月26日付けで懲戒請求者との間で顧問契約を締結し、同年11月9日に懲戒請求者株式会社Aの代表取締役であるBらと面談し、懲戒請求者A社から顧問契約に基づき、元役員Cの問題について調査、検討し、その対処についての助言を求められたところ、Cに対して民事上及び刑事上の責任を追及できる可能性があったものの、Cの問題について検討せず、その対処について懲戒請求者A社に助言もしないまま、時効によりCに対する責任追及ができなくなったため、2019年2月13日付けでBに提出した書面において、顧問料のうち1230万円の不当利益返還義務を認めながら、懲戒請求者A社との返還義務の範囲に関する交渉中、返還義務の一部が時効によって消滅しているという内容の1230万円の返還義務を上記書面で認めていることが時効完成後の債務の承認に当たるかについて検討をしないでいた同年3月1日付けの自身が所属する事務所のD弁護士が作成した意見書を、D弁護士が公正中立な第三者として上記意見書を作成したものと懲戒請求者A社が誤認する可能性がある状況の下で、その内容が不公正な内容であることを知りながら、懲戒請求者A社に提示して、同月12日、懲戒請求者A社との間で、被懲戒者が懲戒請求者A社に150万円を支払う内容の覚書を締結した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条及び第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
なかなか評価が難しい事案です。最終的に「覚書」を作成して解決しているようにみえますが、その覚書の成立過程が問題視されているようにも見えます。また、懲戒事由として、Cに対する請求権を時効にかけたことと、その後の「覚書」作成に関することとは別の事由のようにも思えますが、すべてが1つの事実として記載されています。防御対象としての特定が非常に難しい整理であると感じました。
大阪弁護士会 業務停止1年
被懲戒者は、勾留されているAとの弁護人接見の際、被懲戒者の携帯電話を使用して、2023年3月16日から同年5月13日までの間、20回にわたり、Aに懲戒請求者一般社団法人Bの関係者等と通話をさせた。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
内容としてはけしからんものですが、懲戒請求者が通話の相手方であるという事実もなんとも…。
回数も多く、大胆な方法であることから、どうしても量定が重くならざるを得なくなります。
日弁連の審査請求
1件、処分の変更の公告がありました。
1 裁決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(業務停止3月)を変更する。
(2)審査請求人の業務を2月間停止する。
2 裁決の理由の要旨
(1)原弁護士会は、本件懲戒請求事件につき、家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受け、受遺者の指定がない相続財産がある可能性があるところから、法定相続人である懲戒請求者らから相続手続を受任し、後に同人らから解任された審査請求人について、①委任契約書の作成義務違反、懲戒請求者らに対する②説明義務違反、③報告義務違反及び④財産目録の交付義務違反並びに⑤預り品及び預り金の返還義務違反に加え、⑥受任に当たり、懲戒請求者らと面談せず、受遺者の利益と懲戒請求者らの利益は相反する可能性があることを説明しなかった行為、⑦懲戒請求者らから解任された後、同人らに無断で、Aの遺産の対象外の切手を第三者に交付して処分し、その他の動産も処分した行為について、いずれも弁護士としての品位を失うべき非行に該当するとして、審査請求人を業務停止3月の処分に付した。
(2)本会懲戒委員会が、審査請求人から新たに提出された証拠も含め審査した結果、原弁護士会懲戒委員会議決書(以下「原議決書」という。)の事実認定及び上記⑥及び上記⑦の行為に関する判断には誤りがあるので、改めて認定し、判断する。
(3)原議決書では、審査請求人が、2014年2月3日、家庭裁判所から被相続人Aの遺言執行者の選任を受けたと認定しているが、本会懲戒委員会は、審査請求人が、同日、遺言により指定された遺言執行者への就職を承諾したものであると認定した。
本会懲戒委員会の認定した事実は、上記の点を除き、原議決書の認定のとおりである。
(4)原議決書は、上記⑥の行為について、弁護士職務基本規程(以下「規程」という。)第22条第1項、第28条第3号及び第32条に違反すると判断した。
この点、審査請求人が、受任に当たり懲戒請求者らと面談しなかったことが、規程第22条第1項に違反するとした判断に誤りはないが、審査請求人について、規程第28条第3号に違反する非行事実を認定しているものではないから、原議決書が同号の違反を掲げているのは適切ではない。
また、本件において、受遺者は、遺言執行者である審査請求人の依頼者ではなく、規程第32条が直接適用されるわけではないが、同条の趣旨が、複数の依頼者間に利益の対立が生じるおそれがあるときに、弁護士が受任の時点において採るべき第一次的措置に関して定め、依頼者の自己決定の機会を保障し、依頼者の利益の実現に支障のないようにすることにあること、また、規程第5条の定める誠実義務の趣旨が、依頼者が自己の正当な権利や利益を実現できるようにするために、あらゆることに努めることにあることなどからすれば、審査請求人が、受遺者と懲戒請求者らとの間で利益の対立が生じるおそれがあることを説明しなかったことは、規程第5条及び第32条の趣旨に違反し、弁護士としての品位を失うべき非行に当たる。
(5)原議決書は、上記⑦の行為について、Aの自宅建物内にある動産は、懲戒請求者らが相続すべき財産であったとした上で、審査請求人の上記各処分行為は、規程第5条及び第39条に違反すると判断した。
この点、審査請求人が、懲戒請求者らに無断で、上記約1万円相当の切手を第三者に交付して処分した行為が、規程第5条及び第39条に違反するとした判断に誤りはない。
しかしながら、上記その他の動産については、それが生活動産であり、一般的にはその価額よりも処分に要する費用の方が多額となることが見込まれることからすれば、Aとしては、自宅建物の清算的遺贈について遺言するに当たり、清算的遺贈を円滑に実現するため、生活動産を自宅建物と一体のものとして売却したり、あるいは一括して廃棄したりすることを許容していた可能性は十分にあると考えられる。
したがって、審査請求人が、そのような遺言の解釈に基づき、生活動産を処分したとしても、遺言執行者の裁量の範囲内であると考える余地がある。
なお、仮に、上記その他の動産が、懲戒請求者らが相続すべき財産であったとしても、審査請求人は、動産とともに自宅建物を買受人に引き渡す以前に、懲戒請求者らに対し、引取りを希望する旨の申出がある場合には検討する旨の通知を送付していることからすれば、懲戒請求者らに全く無断で動産を処分したとまでは言えず、他方、懲戒請求者らとしても、処分に費用を要する動産を相続する意思を有していたとは考え難い。
上記から、上記その他の動産について審査請求人が処分したことをもって、弁護士としての品位を失うべき非行であると評価することはできない。
(6)上記本会懲戒委員会の認定と判断に基づき、改めて審査請求人に対する懲戒処分について検討するに、審査請求人には、弁護士としての品位を失うべき非行が複数認められる上、自らの行為について反省の態度も見られないことからすれば、一定の重い処分がなされることもやむを得ない。
しかしながら、上記判断に加え、審査請求人の非行のうち、上記②から⑤までの各業務違反については、いずれも遅きに失しているとはいえ、最終的には義務の履行がなされていることを考慮すると、原弁護士会のなした業務停止3月の処分はやや重きに過ぎるので、これを業務停止2月に変更するのが相当である。
日弁連懲戒委員会が原弁護士会の事実認定について丁寧に再検討し、最終的に業務停止期間を変更しています。また、どうやら懲戒処分後の義務の履行も「いずれも遅きに失している」としながらも考慮要素に加わっていることは検討に値します。