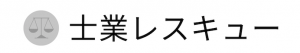コンテンツ
自由と正義2025年10月号
自由と正義の処分内容から、弁護士の懲戒請求対応を学んでいきたいと思います。
今月号は、
単位会の懲戒 9件
| 戒告 | 4件 |
| 業務停止1月 | 2件 |
| 業務停止3月 | 1件 |
| 退会命令 | 1件 |
| 除名 | 1件 |
日弁連
業務停止1月 1件(懲戒しない→異議申出)
審査請求棄却 3件
懲戒しない 2件(戒告→審査請求棄却→東京高裁裁決取消確定→審査請求(処分取消))
単位会の懲戒
東京弁護士会 退会命令
被懲戒者は、所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費を滞納した。
被懲戒者の上記行為は、所属弁護士会の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
会費等の滞納事案です。滞納期間や金額の記載がなく、先例としての評価に困る書き方になっています。
神奈川県弁護士会 戒告
(1) 被懲戒者は、勤務する弁護士法人の支店の唯一の弁護士であり、上記支店においては、1か月約3000件の債権回収を受任し、電話対応担当の事務員が7名という体制であって、上記弁護士法人が病院から未払診療債権の回収を委任したところ、被懲戒者の担当事務員Aに対する指導、監督を怠り、2023年7月26日、Aが上記病院で入院加療を受けた懲戒請求者の息子に対して電話連絡した際、偶然出ただけの懲戒請求者に対し、保証債務の履行を求めて生活状況について聴取し、弁護士に一旦確認することもないまま強い口調で、「生活費から支払え」「娘に支払ってもらえ」「支払わなければ裁判に移行して、弁護士費用とか裁判費用が余分にかかってくるので今のうちに支払った方がよいと思う」などと発言した。
(2) 被懲戒者は、事務員に対する指導、監督を怠り、2021年8月頃から2023年7月にかけて、複数の事務員が、債権債務に関する内容についてのうそや誤りを含んだ行為や態度的な発言を行った。
(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
職務基本規程19条ということは、事務員への指導が問題視されたという事案になります。確かに事務員の行為は行きすぎの面がありますが、本件の評価がこの面だけであったということは、懲戒請求の仕方としてここのみにフォーカスがされていたということでしょうか。
愛知県弁護士会 戒告
(1) 被懲戒者は、弁護士資格を有しないAが、2022年1月6日、投資詐欺被害をめぐり係争中であった懲戒請求者B及びその配偶者CとDとの間の紛争に介入し、Cに示談金額として2000万円を既にDが用意していること等を説明し、Dにその承諾の意向を伝える等の交渉をし、Dが要望する示談の諸条件を調整していたところ、同月7日、Aから懲戒請求者Bらの代理人としてDと示談を締結してほしい旨の電話を受け、Aの行為が弁護士法第72条に違反する疑うに足る相当の理由があることを認識しながら、同月9日に懲戒請求者らと委任契約を締結した。
(2) 被懲戒者は、弁護士資格を有しないAが、懲戒請求者Eから勧誘を受けて出資したFと懲戒請求者Eとの返金をめぐる紛争に介入し、最終的に懲戒請求者EがFに800万円を返金する旨の合意に至ったところ、2022年2月6日にAからFの代理人として懲戒請求者Eと示談を締結してほしい旨の依頼を受けた際、Aの行為が弁護士法第72条に違反する疑いに足る相当の理由があることを認識しながら、Fから示談交渉を受任した。
(3) 被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士職務基本規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
一読して分かりにくい内容となっていますが、要するに、Aという人がBCとDの間の交渉を仲介し((1)の事案)、また、EとFの間の交渉を仲介し((2)の事案)、その交渉成立の場面のみを被懲戒者が受任したというもののようです。Aはいずれも双方代理のようなことをやっていますし、詐欺や出資の被害者側からすれば、すべてが仕組まれたグルのように見えてもおかしくないと思われます。
愛媛県弁護士会 業務停止1月
被懲戒者は、日本司法支援センターに対し、2022年6月6日から同年12月13日までの間に法律相談を行った7名について、実際には法律相談を行っていない日にも法律相談を実施した旨の援助申込及び法律相談票を作成して提出し、法律相談費を請求した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
金額としては3万5000円(税抜き)程度ではありますが、行為自体は詐欺に該当するものであって、厳しい処分もやむを得ない側面はありそうです。
第一東京弁護士会 除名
(1) 被懲戒者は、自ら運用していた弁護士名義のツイッターのアカウントにおいて、地方公共団体の議会の議員が主張していた上記地方公共団体の長による他国の弔慰及び上記地方公共団体の住民による上記議員の解職に関して、2020年12月2日、「気に入らない女性議員を排除したければ、『レイプすればよい』」、「こんなリコールがあること自体、権限・権利の濫用だ」等と投稿し、同月7日、上記地方公共団体について「原発発電等の最終処分場でもしてしまえばどうか」等の投稿を行った。
(2)被懲戒者は、2021年12月頃、懲戒請求者Aから同人を被害者とする強制わいせつ被疑事件の示談交渉等を受任し、2022年4月1日、上記事件の示談を成立させ、加害者代理人弁護士から示談金400万円を預かったが、懲戒請求者Aに対し、これを引き渡さなかった。また、被懲戒者は、懲戒請求者Aに対し、同月2日から同年11月8日までの約7か月間、上記示談金400万円の引渡しに関し、何ら具体的、合理的な説明をしなかった。さらに、被懲戒者は、同月16日、懲戒請求者Aが上記示談金の引渡しを求めるために申し立てた所属弁護士会の紛議調停事件において、紛議調停委員会から依頼及び督促をされたにもかかわらず、答弁書を提出せず、2023年1月12日の上記紛議事件の期日に出頭しなかった。
(3) 被懲戒者は、2022年5月29日、懲戒請求者Bの配偶者及び子から同人らを被害者とする盗撮被害事件の示談交渉を受任し、委任契約書を作成しなかった。また、被懲戒者は、同年6月24日、上記事件の示談を成立させ、加害者代理人弁護士から示談金100万円を預かったが、懲戒請求者Bの配偶者及び子に対し、これを引き渡さなかった。
(4) 被懲戒者は、所属弁護士会から、2022年9月22日に被懲戒者が登録する事務所に到達した通知をもって、預り金の入出金の明細等及び特定の事件について被懲戒者が受領した示談金の入出金の明細等を回答するように求められたが、これに回答しなかった。
(5)被懲戒者は、2022年7月頃、Cから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、同年12月2日、上記事件の示談を成立させ、同月5日には加害者代理人弁護士から示談金100万円を預かったが、Cに対し、これを引き渡さなかった。
(6) 被懲戒者は、2022年10月11日、懲戒請求者Dから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、遅くとも同年12月9日に上記事件の示談を成立させ、加害者から示談金80万円を預かったが、懲戒請求者Dに対し、これを引き渡さなかった。
(7)被懲戒者は、Eから同人を被害者とする痴漢事件の示談交渉を受任し、2022年12月26日、上記事件の示談を成立させ、加害者代理人弁護士から示談金200万円を預かったが、Eに対し、これを引き渡さなかった。
(8) 被懲戒者は、2022年9月3日、Fから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、遅くとも2023年1月13日に上記事件の示談を成立させ、加害者から示談金86万円を預かったが、Fに対し、これを引き渡さなかった。
(9) 被懲戒者は、Gから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、2022年1月23日に上記事件の示談を成立させ、同月25日には加害者代理人弁護士から示談金80万円を預かったが、Gに対し、これを引き渡さなかった。
(10) 被懲戒者は、2023年1月16日、懲戒請求者Hから同人を被害者とするセクハラ事件につき書面の送付及び合意書の作成を受任し、同年2月9日、上記事件の示談を成立させ、遅くとも同月17日には加害者から示談金60万円を預かったが、懲戒請求者Hに対し、これを引き渡さなかった。
(11) 被懲戒者は、Iから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、2023年3月17日、上記事件の示談を成立させ、加害者代理人弁護士から示談金100万円を預かったが、Iに対し、これを引き渡さなかった。
(12) 被懲戒者は、Jから同人を被害者とする盗撮事件の示談交渉を受任し、2023年4月3日、上記事件の示談を成立させ、加害者代理人弁護士から示談金110万円を預かったが、Jに対し、これを引き渡さなかった。
(13) 被懲戒者は、遅くとも2023年3月31日以降、自己の所属する法律事務所が日本弁護士連合会に登録された住所地に所在していなかったにもかかわらず、その事務所を所属弁護士会及び日本弁護士連合会に届け出なかった。
(14)被懲戒者は、2021年9月分から2023年10月分までのうち15か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費合計金42万3500円を滞納した。
(15)被懲戒者の上記(2)の行為は弁談士職務基本規程第44条及び第45条、所属弁護士会の弁談士職務上の預り金品の保管方法等に関する会規第7条並びに所属弁護士会の紛議調停委員会規則第13条及び第14条に、上記(3)の行為は同規程第30条及び第45条並びに同会規第7条に、上記(4)の行為は同会規第10条第1項及び第2項に、上記(5)から(12)までの行為は同規程第45条及び同会規第7条に、上記(13)の行為は弁護士法第21条に、上記(4)の行為は所属弁護士会の会則第24条第1項及び第24条の2第2項並びに日本弁護士連合会会則第95条第1項及び第95条の3第1項に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
非常に懲戒事由自体が多く、またその多くが預り金の不返還であって業務上横領なども疑われる事案であるため、この結論はやむを得ないかもしれません。問題が顕在化した当時、この事務所の費用が極端に安いことが話題になっていました。その結果がこれかとおもうと非常に複雑な気持ちになってしまいます。
大阪弁護士会 戒告
被懲戒者は、A弁護士と共同して、B株式会社の代理人として、懲戒請求者C弁護士等を被告とする損害賠償請求訴訟を提起したところ、相応の根拠のないままに訴訟遂行上の必要性を超えて、懲戒請求者C弁護士が裁判所に虚偽の事実を報告した、裁判官を欺罔した、預金差押中止命令を取したなどと懲戒請求者C弁護士の名誉を著しく害する記載が繰り返し行われている訴状及び準備書面を陳述する等の訴訟活動を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
訴状、準備書面において、行きすぎた表現をしたという事案です。この種の事案の場合、訴訟内において相手方から抗議なり指摘がなされているケースが通常だろうと思われます。そこで素直に撤回なり謝罪なりができず、自己を正当化し強弁に走ってしまうと、行き着くところまで行ってしまいます。
大阪弁護士会 戒告
(1) 被懲戒者は、2020年1月、懲戒請求者から、A株式会社の従業員が過って落下させたビア樽が足に衝突して懲戒請求者が負傷した事故に関する訴訟事件を受任したとこる、懲戒請求者が希望していたB医師による画像鑑定について、同医師による簡易鑑定の結果、足に水が溜まっている程度だと言われたため、鑑定を申し込むことをちゅうちょしていたところ、簡易鑑定による結果を懲戒請求者に伝え、これを踏まえて懲戒請求者と協議した上でB医師に本鑑定を依頼するか否かを決定せずに、2021年8月27日の懲戒請求者の問合せに対し、急ぎの鑑定を申し込んでいる旨の虚偽の説明を行った。
(2) 被懲戒者は、2021年9月、上記(1)の事件について、懲戒請求者の代理人であるC弁護士から解任通知を受領し、懲戒請求者からの預り品であったCD-ROM、領収証等の返還を求められたにもかかわらず、返還に応じなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第36条に、上記(2)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
方針の不安などによって、どうしても「気が乗らない」という事案はありえます。対応が後手後手になってしまい、依頼者に説明ができず、おもわず事実でないことを言ってしまうという例は枚挙にいとまがありません。遅ればせながらであっても、真摯に説明をし、必要な謝罪をすることが求められます。
東京弁護士会 業務停止1月
被懲戒者は、2017年11月1日、株式会社A及びA社の代表取締役の代理人として、懲戒請求者株式会社Bら債権者に対し、破産手続の申立てを受任した旨を通知した後、懲戒請求者B社から再三にわたり問合せや催促があったにもかかわらず、正当な理由がないのに、申立てを行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
本件の懲戒請求者は債権者です。債権者からの問合せや催促にも関わらず、申し立てを行わなかったという事案です。受任通知が2017年ということは、おそらく時効待ちの方針を採用していたものと思われますが、その間の対応に非常に困られたことでしょう。
大阪弁護士会 業務停止3月
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者及びその配供者であるAと2019年9月6日付け委任契約を締結し、同年11月20日及び21日、被懲戒者の指示により、上記委任契約は一旦終了するものの、その後発生する可能性のある費用を含めたものとして、懲戒請求者ら側が被懲戒者に計100万円を預託し、2020年12月7日及び同月24日、懲戒請求者らが預託金100万円の返還を求めたところ、上記委任契約の時間制報酬及び旅費等の実費を控除した残金が存在する可能性があるのに、精算に応じなかった。
(2) 被懲戒者は、2020年9月末日頃、居住していたマンションから住所を移したにもかかわらず、少なくとも9か月以上、転居又は転出を区長に届け出ず、弁護士会への届出もしていなかった。
(3) 被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
確かに、費用の不返還事案ではあるものの、非常に重い処分であると感じました。預託金額が100万円であり、「時間制報酬及び旅費等の実費を控除した残金が存在する可能性」があることは認めているため、実質的な要返還額はさほど高額とは言えない可能性も否定できません。もちろん、「精算に応じなかった」という点が問題視されているわけですので、その点の落ち度はあるかもしれませんが、業務停止3月になる事案には読めませんでした。
また、自宅住所変更の未届けが懲戒事由になった例は、少なくとも記憶にありません。
日弁連の公告
日弁連(異議申出による原決定取消) 業務停止1月
(1) 被懲戒者は、懲戒請求者から遺産分割調停事件等を受任したところ、処理を意し、懲戒請求者側からの再三の問合せに対し調停を申立て済みであると虚の回答をし、その後申し立てた調停事件についても、協議や報告を意し、審判書の送付を遅延し、不服申立手続等の説明を怠ったとして懲戒請求がなされた事件である。原弁士会懲戒委貝会は、被懲戒者が懲戒請求者に対し、上記虚偽の回答をしたことはなく、上記調停事件についても一定の説明はなされており、審判書の送付が遅れたことには相応の理由があるなどと判断し、原弁護士会は、対象弁護士を懲戒しないこととした。
(2) 本会懲戒委員会は、審査の結果、以下のとおり、原議決の認定及び判断を是認することができないとした。
(3) 懲戒請求者が新たに提出した被懲戒者とのやり取りを示す証拠によれば、被懲戒者は、遺産分割調停の申立てをしていないにもかかわらず、申立てをしたと報告し、その後も調停事件の係属を前提に裁判所からの問合せがあった旨を報告し期日指定の見通しを述べるなど虚偽の説明をしたものと言うほかない。
(4) 被懲戒者は、その後、遺産分割調停の申立てをしたが、事件が調停に代わる審判に移行したところ、懲戒請求者に対し、審判手続の説明やこれに対する懲戒請求者の意向の確認をしておらず、また、審判書を受領してから10か月間これを異議申出人に送付しなかった。この点について、原弁護士会懲戒委員会は、当該審判書が結果的に無効であったので懲戒請求者に混乱が生じることなどを避けるためもあり、不交付には相応の理由があったとするが、被懲戒者は、審判書が無効である理由を説明した上で、今後の方針を説明し、協議をすれば足り、また、そもそも、対象弁護士がこの時期に審判書の無効を認識していたとは認め難い。
(5) 被懲戒者は、その後、新たに有効な審判書(以下「新審判書」という。)を得たが、これを懲戒請求者に交付するに当たり、異議の申立ての方法等について説明し、協議していない。この点について、原弁護士会懲戒委員会は、懲戒請求者が被懲戒者に不満を伝えたことはないこと等を理由として非行に当たらないと判断した。しかし、本件は、親族の関係が複雑で、感情的な対立も顕著であり、しかも、本件懲戒請求事件の前に同じ相続事件に関して懲戒請求者の親族から被懲戒者に対して懲戒請求がなされた際、被懲戒者が謝罪し、以後速やかな事件処理並びに適切な報告及び協議を約したことから懲戒請求が取り下げられ、原弁談士会網紀委員会が懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする旨議決している。このような経緯に照らせば、新審判書の内容について法的には争う余地がほぼないとしても、懲戒請求者の希望を尊重するためにも、十分な説明と協議が求められていたと言うべきである。
(6) したがって、被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第5条に、上記(4)及び(5)の行為は同規程第36条に違反し、被懲戒者が原弁護士会及び本懲戒委員会において不合理な弁解を繰り返していること、被懲戒者は同じ相続事件について別件の懲戒請求を受けた際に速やかな事件処理並びに適切な報告及び協議を約したにもかかわらず本件に至ったことなどの事情を考慮すると、被懲戒者を懲戒しないとした原弁護士会の決定を取り消し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。
原弁護士会(福岡県弁護士会)懲戒委員会が「懲戒しない」と決議したものに対し、懲戒請求者から異議の申し出があり、日弁連懲戒委員会が原決定を取り消して「業務停止1月」としたという珍しい事案です。
内容から推測するに、前回の懲戒請求事案で、謝罪の上、速やかな報告等を約束していたにもかかわらず、それでも依頼者との間の円滑なコミュニケーションが取れないまま、手続を進めてしまったというもののようです。
本件においては、原弁護士会において一旦は飛鳥会社側の弁解が通っていたことから、日弁連の異議申出においても同様の弁解を繰り返したものと推測されますが、それが通らないとなると、一転「不合理な弁解を繰り返している」という評価につながってしまいます。
強弁の怖いところでです。
審査請求(処分取消) 原処分 戒告 (2件)
- 裁決の内容
(1) 審査請求人に対する懲戒処分(戒告)を取り消す。
(2) 審査請求人を懲戒しない。- 裁決の理由の要旨
(1) 本件は、審査請求人が、原弁談士会から戒告の懲戒処分(以下「本件懲戒処分」という。)を受け、本会に対し、審査請求をしたところ、本会から審査請求を棄却する旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けたため、東京高等裁判所に本件裁決の取消しを求める訴えを提起し、同裁判所は、本件裁決を取り消す旨の判決(以下「本件判決」という。)をなし、本件判決が確定したものである。
(2) 本件裁決の概要は以下のとおりである。
一般に、企業、大学等の法人(以下「企業等」という。)がハラスメント行為、公益通報、不祥事等について、その調査、対応等のために設置する委員会、調査会、相談窓口等の機関(以下「委員会等」という。)において、弁護士が中立・公正な立場で一定の事実調査、法的判断等の職務を行った場合に、弁護士の職務の公正さやそれに対する言頼への観点から、その後に企業等の代理人となったことに問題はなかったかどうかを考えるに当たっては、その委員会等が設置された目的や態様への考慮のみならず、当該弁護士の委員会等における立場、申立てをした者及び申し立てられた相手方に対する説明内容、その後に代理した事件の性質や審理状況、その事件における当該弁護士の活動内容等、それぞれの案件に現れた諸般の事情を総合的に勘案、考感して判断する必要がある。
審査請求人は、同じ法律事務所に所属するA弁護士が、懲戒請求者の雇用主である法人(以下「本法人」という。)が設置するハラスメント相談窓口の代行者として懲戒請求者から事情を聴取したことを、認識し、又は認識し得たにもかかわらず、懲戒請求者が本法人を被告として提起した地位確認等請求訴訟(聴取した事実関係と同一の事実を含む事実関係に基づく損害賠償請求を含む。)の本法人訴訟代理人弁護士として、懲戒請求者の主張を争ったことは、審査請求人が当然期待されるべき弁護士の職務の公正さやそれに対する信頼を損なうものであり、弁護士職務基本規程第5条に違反する。
(3) これに対し、東京高等裁判所は、A弁護士が本法人の設置する委員会等において、中立・公正な立場で一定の事実調査、法的判断等の職務を行ったものであるとは認め難いとし、本件裁決は、重要な事実関係について、事実の基礎を欠くものであり、違法なものであるとした。
(4) 本会懲戒委員会は、本件判決の趣旨に従い、改めて審査した結果、本件判決の判断に依拠して、次の各事実を認定した。
① A弁護士は、2017年7月5日及び同年9月1日の2回、審査請求人及びA弁護士が当時所属していた法律事務所において、懲戒請求者と面談し(以下2回の面談を併せて「本件面談」という。)、その際に聴取した内容を客観的に整理して本法人に伝えた。
② A弁護士は、懲戒請求者が申告したハラスメントについて、本法人の依頼を受けて、その事実関係の有無等を調査したり、法的判断等を行ったりしたことをうかがわせる証拠は見当たらない。
③ 以上より、A弁護士が、本法人の設置する委員会等において、中立・公正な立場で一定の事実調査、法的判断等の職務を行ったものであるとは認められない。
④ 懲戒請求者は、本件面談時、A弁護士の役割について、ハラスメントの被害を申告する者及びその相手方並びに本法人との間において一定の中立・公正な立場に立つものであると認識していたとは認められず、本件面談の前後に懲戒請求者と本法人の人事部との間でやり取りされた電子メールの内容からも、懲戒請求者がそのような認識をしていた事実は認められない。
(5) 以上の事実認定に基づき、審査請求人に対する懲戒処分の要否について改めて検討するに、A弁護士が本法人の設置する委員会等において、中立・公正な立場で一定の事実調査、法的判断等の職務を行ったものであるとは認め難いとされた本件については、本件懲戒処分を維持することは相当ではない。したがって、審査請求人を懲戒しないことを相当と判断した。
懲戒を受けた弁護士は、まずは日弁連に対し審査請求を行う必要があります(いきなり訴訟提起をすることはできません)。審査請求の裁決においても望むような処分の取消、変更がなされなかった場合、東京高裁に裁決取消訴訟をすることになります。
東京高裁は処分の取消をするかどうかのみを判断しますので、取消判決が確定した後は、改めて日弁連の審査請求に戻り、日弁連懲戒委員会が裁判所の判決を踏まえて議決をします。
本件も、審査請求の棄却裁決に対して、東京高裁が裁決を取り消したため、あらためて日弁連が「懲戒しない」旨の裁決を行ったというものです。
ご推察のとおり、裁判所は、弁護士自治を非常に重視しますので、弁護士会に広汎な裁量を認め、日弁連の裁決が事実上又は法律上の基礎を欠いてその裁量を逸脱する場合にのみ取消がなされます。
審査請求人(及び、就いておられるであろう代理人)の先生方には、心から賛辞を送りたいとおもいます。本当に素晴らしいです。