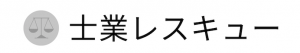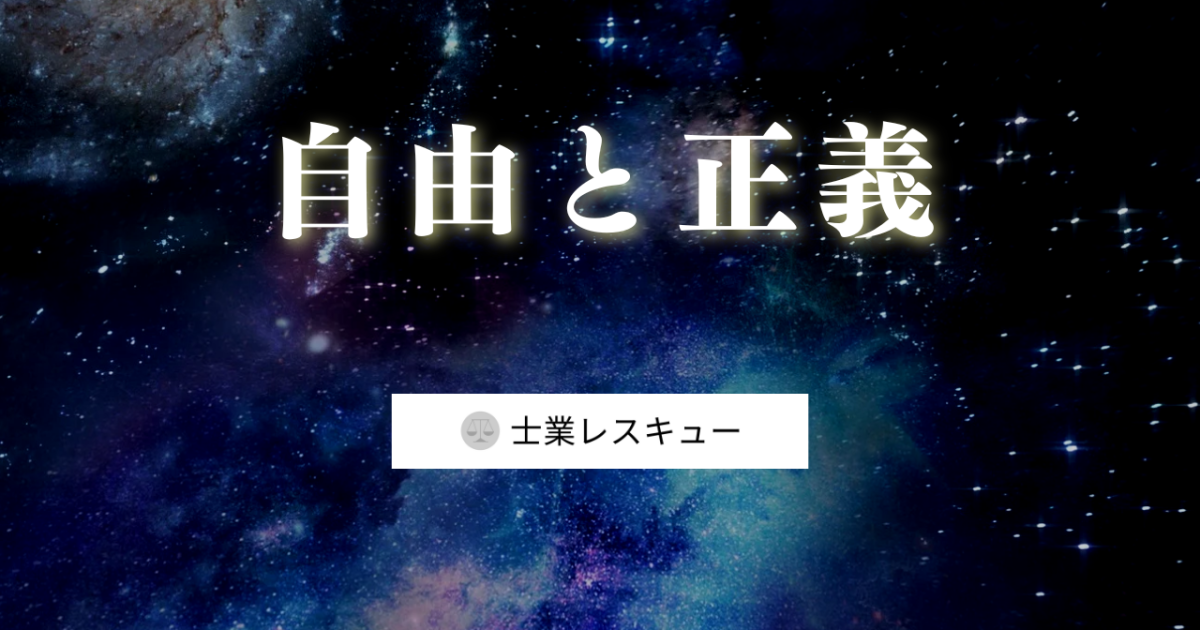最近は、弁護士の横領や非弁業者に取り込まれた弁護士の話題などの報道を目にするようになってきました。
今月の自由と正義が手元に届きましたので、まとめておきます。
コンテンツ
自由と正義2025年5月号
自由と正義2025年5月号は、戒告4件、業務停止20日 1件、1月2件、3月2件、退会命令1件の合計9件でした。
単位会の懲戒
千葉弁護士会 戒告
- 懲戒請求者に対する事件の報告がないとのことで起こされた紛議調停において、受任事件について少なくとも1か月に1回書面により報告するという調停が成立、その後、不当利得返還請求事件では答弁書に対する反論等を行わず敗訴し、損害賠償請求権を時効消滅させたため控訴するも控訴理由書を提出せず、また、別件の損害賠償請求事件においては支払督促申立てが不送達で却下、再度の申立ても委任状を取得しながら着手せず、また処理状況について懲戒請求者に報告しなかった
というもの。
懲戒請求者と各紛争当事者が異なるようにも見え、どうして懲戒請求者に対して報告義務が生じるのかが理由の要旨からは読み取れませんでした。
岐阜県弁護士会 退会命令
- 会費滞納18か月分
仙台弁護士会 戒告
- 懲戒請求者と財産管理等委任契約を締結、450万円を預かったが、その後解除されたにもかかわらず返還せず、また、遅延損害金等を含む約665万円を支払う旨の訴訟上の和解が成立したものの期限までに支払わなかった。
というもの。
この結論になったということは、最終的には無事に返還したものと思われます。
京都弁護士会 業務停止3月
- 2020年9月に貸金返還請求事件を受任したが、2023年11月に委任関係が終了するまで2年7か月にわたり訴訟提起しなかった。
- 上記事件に関し、懲戒請求者からの連絡に応答せず、面談の約束を当日にキャンセル、電話に出ても即座に切るなど、連絡を拒絶または回避する態度を示し続けた。
- 委任契約の合意解除後、通知書等の原本の返還を求められたが応じなかった。
- 紛議調停の呼出に応じなかった。
というもの。
紛議調停の対応が懲戒請求の呼び水になってしまったかもしれません。仮に懲戒請求と紛議調停の申立てが同時にされていたとしても、紛議調停の対応は最後に与えられたチャンスです。逃さないようにしましょう。
第一東京弁護士会 業務停止3月
- 法的助言を含む委任契約の受任者たる地位を、被懲戒者が代表を務める弁護士法人ではない会社(C社。イギリス領ヴァージン諸島法人)に変更、報酬を同社に取得させた。
- 成功報酬の基礎となる経済的利益の額について、懲戒請求者の解釈と合致していないことを認識しながら、十分な説明を尽くさず、事前の協議もなくC社の代表者として報酬請求を行い、期限までに支払いがなされない場合は高額の遅延損害金の発生や株主代表訴訟が提起される可能性を示唆して支払いを催促した。
というもの。
前者の事由については、自社が経営する会社との非弁提携(規程11条)、報酬分配(規程12条)、違法行為の助長(規程14条)、品位を失う事業への参加(規程15条)、営利業務従事における品位保持(規程16条)を認定されており、非常に珍しい類型です。
広島弁護士会 戒告
- 懲戒請求者からの電話で言われたことをきっかけに憤慨し、懲戒請求者を威圧するために木刀を携行して懲戒請求者宅に向かい、同人を呼び出し、これに応じて出てきた同人と口論及びもみ合いになった際にも木刀を所持していた
というもの。
なんともコメントに困りますが、おそらく業務と関係のない行為だと思われます。
第二東京弁護士会 業務停止1月
- 控訴判決に対する上告及び上告受理申立てを受任したが、上告理由書、上告受理申立理由書の提出期限を徒過したため却下決定がなされたが、懲戒請求者に報告をせず、問合せに対して未だ結果は出ていない旨の当座しのぎの虚偽の回答を繰り返し、懲戒請求者が自ら裁判所に問い合わせて却下決定を確知するまで1年7か月以上にわたって真実の顛末を報告しなかった。
- 上記事件により回収した約22万を、却下決定がなされた時点で速やかに返還すべきところ1年近く返還しなかった。
- 預り金を一定期間目的外に利用した。
というもの。
最初のミスを隠したりごまかしたりすると、傷口が広がってしまうという例です。
岡山弁護士会 業務停止20日
- 2020年3月、住宅ローン特別条項付の個人再生事件を受任したが、2021年2月に面談を行った以外具体的な打合せをせず、2021年4月まで再生申立てを行わず、同年10月に申立てを取り下げてから2022年8月まで再度の申立てをしなかった。
- 2021年4月付け取下げについて懲戒請求者の同意を得ておらず、取下げから8か月以上も、市民窓口に相談されるまで取下げの報告をせず、2023年10月、懲戒請求者と協議し、同手続きが認可される可能性がほとんどなく裁判所から取下げを強く求められていることを説明したが、同11日、十分な説明ないし意思確認を怠り、懲戒請求者の明確な同意を取ることなく取り下げた。
- 申立てに必須な不動産評価の調査を行わなかった。裁判所に提出した陳述書に、再度の個人再生手続きではないとの記載をした。
- 委任契約書を作成しなかった。
というもの。
業務停止20日という、極めて珍しい量定です。個人再生事件自体は一定の時間を要する類型であるものの、調査不足や説明不足という要素が重視されたものと思われます。
東京弁護士会 業務停止1月
- 2013年9月には、A社、B社、C(A社、B社の代表者)、D(A社、B社の連帯保証人)の債務整理または破産手続申立事件を受任したが委任契約書を作成しなかった。
- 着手金及び預り金として合計500万円を受領したが、6年以上もの間、C、A社、B社の破産申立てをしなかった。
- 2019年11月25日、C、A社、B社から解任通知を受けたが、裁判所に郵送した破産申立書一式について裁判所に連絡するなどの措置を講ずることなく、申立代理人としての権限を失っていた同26日に申立書類を裁判所に受理させた。
- 2019年11月27日、新しい代理人から500万円と関係書類の返還を求められたにもかかわらず、預り金等については2020年12月30日まで精算せず、関係書類については返還しなかった。
- Dについては2018年に破産申立てを行い、2019年に免責許可決定がなされて終了したが、返還するべき預り金を2024年10月31日まで精算しなかった。
というもの。
契約書不作成の問題点の1つは、契約上何をするべきかが書面上明確にならないことです。2013年時点で被懲戒者としては、A社、B社、Cの破産申立てについても明確に受任していたと認識していたかが不安な事実関係に見えますね。
大阪弁護士会 戒告
- 相手方が提出した意見書に対して、準備書面において「報酬を得る目的で、結論先にありきの意見書を出しているに過ぎず、まさに「鑑定屋」と呼ぶにふさわしい」、「被害者を助けようとか、被害者に寄り添おうとする意思など全くない医師である」と表現方法として著しく相当性に欠ける記載をした。
というもの。
筆が滑ったのでしょう。この表現をして裁判所が理解してくれるか、を冷静に見極めたいところです。
日弁連以降
紹介するもの以外に、審査請求棄却が3件、裁決取消訴訟の判決確定(棄却)が2件あります。
長崎県弁護士会 戒告→ 異議の申出 業務停止1月
単位会
- 被懲戒者の実母の後見事務の処理方針について、成年後見人弁護士である懲戒請求者と対立し、後見事務を次々に妨害したという事案
- より重い懲戒処分も考えられたが、懲戒請求者の対応にも問題があり、被懲戒者の行きすぎた行動を誘発した側面があるとして戒告を選択
日弁連
- 原弁護士会の判断は誤り
- 被懲戒者は、被後見人宛の郵便物の転送先や住民票上の住所を被懲戒者宅に変更、サ高住に入居させ、被後見人には判断能力があると主張し実母の代理人として懲戒請求者に対して種々の要求を繰り返した。この間、懲戒請求者は、被懲戒者や他の親族から後見事務への協力が得られず、次々と起こる事態に対応を余儀なくされており、関係者から意見を聴取して協議することは困難だった。その困難はむしろ被懲戒者の行為に起因しており、懲戒請求者の対応が被懲戒者の非違行為を誘発したと評価することはできない。
- 被懲戒者には一定の反省も見られ、同様の飛行が繰り返されるおそれはないと思われることを考慮しても、その非行の程度は軽いものとは言えない。
というもの。
懲戒請求者は弁護士なので、戒告の懲戒処分に対して異議の申出まではなかなかしないでしょう。ただ、単位会懲戒委員会の議決内容があたかも自己が誘発したものと認定されては異議の申出をせざるをえないという判断になったものと思われます。ある意味、弁護士会が誘発した異議の申出といえるかも知れません。
第一東京弁護士会 業務停止2月→審査請求 業務停止1月
原弁護士会
- 審査請求人が懲戒請求者との間の通話を無断録音し、その録音された通話を記載した報告書を懲戒請求者に無断で裁判所に提出して懲戒請求者の秘密を漏洩した行為が弁護士法23条及び職務基本規程5条に違反するとして業務停止2月に
日弁連
- 原弁護士会は、会話の無断録音が適法なものとして許容されるためには「公益を保護するため、あうりは著しく優越する正当利益を保護するためなどの特段の事情が存する」ことが必要判断するようであるが、弁護士の活動において証拠の保全が必要となる場面は多く認められ、証拠の保全を目的として会話を録音することが弁護士として正当な業務行為に当たると解される場合が相当程度あることから、適法性の要件を限定的に解するのは妥当ではない。
- 審査請求人が通話を録音した目的は不当なものではなく、録音に至る経緯についても不適切なところはない。
- 本件において問題になるのは、録音された通話を懲戒請求者の承諾なく報告書にまとめて裁判所に提出した行為である。
- 原弁護士会の処分の判断には誤りがあり、業務停止2月は重きに失する。しかし、審査請求人の行為は重大な非行であり、反省の意も十分なものとは言えないことなどの事情に鑑みれば、業務停止1月が相当。
というもの。
録音行為自体は正当な業務行為であるという認定はそのとおりで、正しいものと考えます。
ただ、録音した内容を無断で報告書に記載し裁判所に提出した行為のみで、業務停止1月は、それでもやや重い印象です。「反省の意も十分なものとは言えない」とわざわざ記載されていることからも、日弁連の懲戒委員会が重視するポイントが見えてきます。