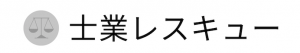弁護士会による弁護士の懲戒手続きについて解説していきます。
なお、本稿は「弁護士懲戒手続の研究と実務」(第三版 日本弁護士連合会調査室)を参考にしています。
コンテンツ
弁護士懲戒制度について
弁護士自治との関係
弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とし、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならないとされています(弁護士法1条)。
社会の弁護士に対する信頼を維持し、向上させるために、弁護士に対する指導監督が十分に行われる必要があります。
国家権力と国民の基本的人権とが衝突する場合、弁護士が裁判所や法務大臣の監督に服していたら、その使命を全うすることが難しくなり、ひいては国民の基本的人権に対する侵害にもつながりかねません。
そこで、弁護士会や日弁連が弁護士に対する監督権、懲戒権を有する弁護士自治が認められたのです。
弁護士自治に基づく弁護士懲戒制度は公益的見地に基づくものとされています。実態として、弁護士が携わった事件の関係者が、その被害の救済や被害感情の満足を目的として懲戒請求がなされることがありますが、そうした機能は副次的なものに過ぎません(懲戒請求が取り下げられても、懲戒手続きが終了しないのはそのため。)。
懲戒処分の性質
弁護士に対する懲戒処分は、弁護士会及び日弁連に付与された公の権能に基づいてなされる広義の行政処分にあたります。懲戒された弁護士等が、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができ(同法59条)、取消訴訟を提起することができる(同法61条)のもこのためとされています(最大判昭和42年9月27日)。
また、弁護士に対する懲戒処分と刑罰はその目的、性質を異にすることから、両方が併科されることはありえます(最判昭和29年7月2日)。
懲戒手続きの流れ
おおまかな流れ
弁護士に対する懲戒請求がなされた後の流れは次のとおりのフローチャートになります。
弁護士会の懲戒手続き
懲戒請求
懲戒請求は「何人も」することができます(法58条1項)。利害関係のない第三者でも可能です。
もっとも、昨今問題になっている濫訴的懲戒請求の影響もあり、懲戒請求に本人確認資料を求める弁護士会も出てきています。
なお、懲戒請求者は懲戒手続きにおける「当事者」ではありません。調査開始通知書や決定の通知は送付されますが、手続きに関与する権利があるわけではありません。
一定の場合に、日弁連に対し、異議の申出(法64条1項)、や綱紀審査の申出(64条の3第1項)をすることは可能です。
また、懲戒請求を取り下げることも可能ですが、懲戒請求の取下げや懲戒請求者の死亡によって懲戒手続きが終了することはありません。死亡によって懲戒請求者の地位を相続人が承継する、ということもありません。取下げ後は懲戒請求者として決定の通知なども送付されません。
弁護士に対して懲戒処分を受けさせる目的をもって、虚偽の事実を申告して懲戒請求した懲戒請求者については、刑法172条の虚偽告訴等の罪が成立するものと解されています。
弁護士会は、この懲戒請求があったとき、綱紀委員会に事案の調査をさせることになります(法58条2項)。
しかし、それ以外に、弁護士会は「所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき」も綱紀委員会に事案の調査をさせなければなりません(いわゆる「会請求」、「会立件」。)。この会請求による懲戒請求にあたっては、弁護士会が事案の調査を事前にするのは好ましくないため(綱紀委員会の調査の先取りになってしまうため)、そうした独自の調査を要さない会費滞納や倫理研修受講違反など会則違反の場合になされています。
対象弁護士
弁護士会が懲戒手続きを開始するための要件として、対象弁護士が
①弁護士であること
②その弁護士会に所属していること
が必要になります。
弁護士であること
①については、特定の弁護士について複数の懲戒請求が審査されていて、そのうちの1つについて退会命令か除名の懲戒処分が告知されたときが問題になります。
後述するとおり、告知によって直ちに処分の効力が発生するという現在の考え方によれば、退会命令や除名の懲戒処分の告知地とともに弁護士ではなくなるため、他の懲戒手続きについては、「対象弁護士の弁護士たる資格喪失により終了した」との議決がなされ、終了することになります。その後、審査請求などにより、退会命令や除名の懲戒処分が変更され、弁護士たる身分が回復したとしても、一旦終了した手続きが復活することはないと考えられています。
その弁護士会に所属していること
②については、登録替えの問題に関連します。
懲戒の手続きに付された弁護士は、懲戒逃れを防ぐため、登録替えや登録取消の請求ができません(法62条1項)。
しかしながら、たまたま登録替えの手続きが完了した後で懲戒請求がなされた場合など、その弁護士会に所属しない弁護士に対する懲戒請求になることがあります。
その場合、対象弁護士の適格性を失い、その弁護士会は懲戒できないことになります。
除斥期間
懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができないことになっています(法63条)。
いわゆる3年の除斥期間を定めたものですが、「懲戒の事由があったとき」の解釈と、「懲戒手続き」を開始することの解釈がいずれも問題になります。
「懲戒の事由があったとき」の解釈
「懲戒の事由があったとき」、すなわち除斥期間の始期ですが、これは懲戒事由たる行為が終了したとき、と解釈されています。
例えば、預り金を着服したまま返還しない、という事由の場合、返還時が始期となります。着服時ではないので、返還しなかった場合、いつまで経っても除斥期間が進行しないことになります。
また、行為の態様によっては、複数の行為が「一体のもの」として全体が1つの懲戒請求事由と評価されることがあります。その場合、事実上3年以上前の行為も審査の対象になることはありえます。
「懲戒の手続」の解釈
「懲戒の手続」とは、(懲戒委員会の事案の審査ではなく)「綱紀委員会の調査」を言います。
懲戒委員会の調査に付された時点で3年経っている事由については懲戒手続きを開始することはできません。
ここで注意したいのは、「懲戒請求をしたとき」が基準ではないことです。通常、弁護士会が懲戒請求を受理してから、綱紀委員会の調査に付するまで、数日のタイムラグがあります。この間に3年が経過してしまうことが時々あります。
綱紀委員会の調査
綱紀委員会の役割
懲戒請求を受けた弁護士会は、いきなり懲戒委員会の審査に付するのではなく、まず綱紀委員会の調査に付することになります。
これは、懲戒請求の濫用による弊害を防止するためであると同時に、一定の懲戒不相当事由を早期に排除して懲戒委員会の審査を充実させる目的があると言われています。
綱紀委員会の調査は、言ってみれば「あらごなし」の役割を求められているのです。
綱紀委員会委員の構成
弁護士会の綱紀委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者で構成されています(法70条の3)。
綱紀委員会の委員は、刑法上の「公務に従事する職員」とみなされます(刑法7条1項)。したがって、公務執行妨害の対象となったり、贈収賄の主体になったりします。
調査権限
綱紀委員会は、調査又は審査に関し必要があるときは、対象弁護士等、懲戒請求者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができるとされています(法70条の7)。
弁護士がこれらの提出を求められた場合は、正当な事由がない限り、これに応じる義務があります。
また、各弁護士会の会規によって、対象弁護士の審尋、関係人の審尋、物の検証や鑑定の嘱託などができるとされていることがあります。
調査の流れ
まず、綱紀委員会の調査は、懲戒請求者、対象弁護士等、懲戒事由に該当する事実が特定されているかどうか等を実質的に調査することになります。特に、懲戒事由に該当する事実の特定は、対象弁護士の防御の対象を明示することになり、また議決の効力が生じる範囲を画するなど極めて重要な意義を有するため、格別な留意が必要になります。
次に、対象弁護士に弁明書の提出を求めて、争点を整理します。事案によっては、懲戒請求者、対象弁護士、参考人らを呼び出してその供述を聴取して調書を作成したり、証拠の提出を求めるなどして、懲戒事由に該当する事実が存在するか、それが非行に当たるかなどを調査します。除斥期間についても実質的に調査します。
調査が完了すれば、綱紀委員が議決書案を作成(通常は委員の中から主査を決めて、議決書の案を作成させることになります)し、これを元に綱紀委員会に報告させ、委員会において議決する流れになります。
委員会の議事は原則非公開です。
記録の閲覧謄写については、対象弁護士に対しては適正手続きの観点から許可されますが、懲戒請求者等に対しては委員会の裁量に委ねられています。
懲戒請求の取下げ、請求者の死亡
対象弁護士等と示談が成立するなどして、懲戒請求が取り下げられたとしても、懲戒手続きには何らの影響も及ぼしません。懲戒請求者の死亡の場合も同様です。
懲戒手続きが公益的な目的に基づくもので、懲戒請求は、調査開始の端緒に過ぎないからです。
もっとも、示談の成立や懲戒請求の取下げの事実を対象弁護士に有利な情状として斟酌することは可能です。
綱紀委員会の議決
綱紀委員会は調査を終了すると、対象弁護士等に対して懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるかどうかの議決をすることになります。
議決の種類は次のとおりです。
①「懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める」
②「懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」
③「本件懲戒手続は、【対象弁護士の死亡/弁護士資格の喪失_/弁護士の身分の喪失】により終了した」
綱紀委員会の議決がなされ、弁護士会に報告されると、弁護士会はその結果に拘束されます。
①の場合は、懲戒委員会に事案の審査を求める(懲戒請求事由の一部のみ求めることが相当であればその部分のみの審査を求めることになります。)、②の場合は、対象弁護士を懲戒しない旨の決定をすることになります。
不服の申立
懲戒委員会に事案の審査を求める決定がなされた場合であっても、対象弁護士等は不服の申立はできません。改めて対象弁護士の弁明を含めて懲戒委員会で審査がなされることになります。
他方、懲戒請求者は懲戒しない旨の決定に対し、日弁連に対して異議の申出をすることができます(法64条)。異議申出期間内(通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内。)に日弁連に対して異議の申出ができる旨を教示しなければなりません。
懲戒委員会の審査
懲戒委員会の役割
弁護士会が所属弁護士を懲戒するには、懲戒委員会の議決に基づかなければなりません(法58条5項)。つまり、弁護士を懲戒するかどうかの実質的な判断をするのが懲戒委員会ということになります。
懲戒委員会は弁護士会から独立して、懲戒権を適切かつ公正に行使することが求められます。
判例上、具体的事件の審査に、弁護士会会長その他の理事者が理由なく出席して意見を述べることは許されないという事案があります(東京高裁昭和42年8月7日)。
懲戒委員会委員の構成
弁護士会の懲戒委員会の委員は、弁護士、裁判官、検察官及び学識経験者で構成されています(法66条の2)。
懲戒委員会の委員は、刑法上の「公務に従事する職員」とみなされます(刑法7条1項)。したがって、公務執行妨害の対象となったり、贈収賄の主体になったりします。
審査の流れ
弁護士会は、綱紀委員会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当とする議決があったときは、これに拘束され、懲戒委員会に速やかにその審査を求めなければなりません(法58条3項)。
懲戒委員会は、審査の期日を定め、対象弁護士に対しその旨を通知します。対象弁護士の期日出頭権及び陳述権の機会の確保の目的です。
審査期日とは、懲戒請求事案を審査するに際して、対象弁護士、対象弁護士法人の社員、懲戒請求等の関係人の審尋、その他主として証拠を採取する手続等の行為を行うため、懲戒委員会の委員、対象弁護士、対象弁護士の社員その他関係者が一定の場所に会合する日をいうものです。この審査期日は、主として対象弁護士等の弁明を聴き、有利不利な証拠を採用するものであるから、手続的な保障が求められ、多くの弁護士会においては、審査期日における審査をした後でなければ対象弁護士等を懲戒することを相当と認める旨の議決をすることができないとされています。
懲戒委員会の審査は原則として職権で行われますが、対象弁護士には陳述権(弁明すること、証拠の申出をなすこと、参考人その他に質問をすること等が含まれる)が認められています。
審査期日においては、審査期日調書が作成されますので、対象弁護士は閲覧謄写をしておくべきです。
刑事訴訟と懲戒手続の中止
懲戒委員会は、同一の事由について刑事訴訟が係属する間は、懲戒の手続を中止することができます(法68条)。
手続を中止することは懲戒委員会の任意ですから、審査を進めることは可能です。
なお、法律上は、「刑事訴訟」の係属が必要ですので、単に捜査されているとか、逮捕されたというのみでは足りません。
懲戒請求の取下げ、請求者の死亡
綱紀委員会と同様、対象弁護士等と示談が成立するなどして、懲戒請求が取り下げられたとしても、懲戒手続きには何らの影響も及ぼしません。懲戒請求者の死亡の場合も同様です。
懲戒手続きが公益的な目的に基づくもので、懲戒請求は、調査開始の端緒に過ぎないからです。
もっとも、示談の成立や懲戒請求の取下げの事実を対象弁護士に有利な情状として斟酌することは可能です。
懲戒委員会の議決
懲戒委員会は審査の上、対象弁護士等に対して懲戒処分をするべきかどうか、処分するとして法57条所定のいずれの処分を選択するか、さらに業務停止を選択する場合その期間をどれほどにするか、を議決しなければなりません。懲戒委員会はこの議決をしたら速やかに議決書を作成しなければなりません(法67条の2)。
議決の種類は次のとおりです。
①「対象弁護士等を除名することを相当とする。」
②「対象弁護士等に対し、退会を命ずることを相当とする。」
③「対象弁護士等に対し、業務を○年○月停止することを相当とする。」
④「対象弁護士等を戒告することを相当とする。」
⑤「対象弁護士等を懲戒しないことを相当とする。」
⑥「本件懲戒手続は、【対象弁護士の死亡/弁護士資格の喪失_/弁護士の身分の喪失】により終了した」
懲戒委員会はこれらの議決の結果を弁護士会に報告しなければなりません。弁護士会は、この議決に拘束され、総会等によってもこれを変更することはできません。
懲戒委員会議決後の手続
懲戒するとき
弁護士会は、対象弁護士を懲戒するときは、対象弁護士等に懲戒の処分内容及びその理由を書面により通知しなければなりません。具体的には「懲戒書」を作成し、対象弁護士を言渡期日に呼び出し、懲戒書を読み上げて言渡をした上で懲戒書の正本を送達するか、言渡をしないで正本を送達することになります。
対象弁護士が言渡期日の呼出に応じない場合、送達の日を告知日とすることになります。
懲戒請求者に対しても懲戒書の謄本を送付します。除名以外の懲戒処分に対しては、異議申出期間内(懲戒した旨の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内。)に日弁連に対して異議の申出ができる旨を教示しなければなりません。
懲戒しないとき
懲戒請求者に対しては、懲戒しない旨の決定をしたことの通知と議決書の謄本を送付します。また、異議申出期間内(懲戒した旨の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内。)に日弁連に対して異議の申出ができる旨を教示しなければなりません。
対象弁護士等に対しても、議決書の謄本とともに通知をします。
懲戒処分の内容
懲戒処分の効力発生時期
懲戒処分はその告知が行われたときに直ちに効力が発生します(最大判昭和42年9月27日)。処分確定時ではありません。
懲戒処分の種類(弁護士)
戒告
弁護士に反省を求め、戒める処分です。
弁護士会が対象弁護士に処分告知をした段階でその効力が生じ、同時に終了します。したがって、執行停止、効力停止の申立てはできません。
戒告は、対象弁護士の身分や弁護士となる資格に対して全く影響を及ぼすものではなく、弁護士活動に制限を及ぼすものではありません。
ただし、戒告の処分を受けた者は、3年間日弁連会長選挙の被選挙権を失う(会長選挙規程14条1項)ほか、弁護士会の法律相談等の名簿登載の抹消などの不利益を被ることがあります。
2年以内の業務の停止
1か月以上2年以内の期間、弁護士業務を行うことを禁止する処分です。期間は月または年単位で定められます。初日算入によって計算します。
業務の停止は、その処分告知とともにその効力を生じるので、執行停止・効力停止の決定を得られなければ、その処分の効力は停止されません。
業務停止中の業務は新たな懲戒事由になりうるとともに、行為そのものが違法な職務行為になりえます。
業務停止中も弁護士会の会員の身分は維持されるので、弁護士会費は発生します。
なお、業務停止中に登録取消しをすることは可能で、取り消した時点で業務停止の懲戒処分の効力は失効します(昭和59年3月3日付け日弁連会長通知)。
業務停止期間中は次のとおりの措置を取らなければなりません。
被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準(外部リンク)
① 委任契約の解除
・委任契約を直ちに解除、解除後、係属する裁判所等に辞任の手続を執らなければならない。
・1か月以内の業務停止の場合で、依頼者が継続を求め、その旨を記載した確認書を作成し、弁護士会に写しを提出する場合は解除しないことができる。ただし、依頼者に対して委任契約の継続を求める働きかけをした場合はこの限りでない。委任契約を継続するときは、継続確認後直ちに、係属する裁判所等に対し処分を受けたこと及び業務停止の期間を通知しなければならない。
・解除した委任契約が債務整理事件であるときは、債権者に対し、委任契約を解除したことを連絡するものとし、和解が成立した債権者に対する弁済代行ができないことを通知する(支払期限が処分の効力が発生した日から10日以内の場合は弁済代行できる。)。
② 顧問契約の解除
③ 期日の延期、変更申請の禁止。裁判所からの送達等受領の禁止
④ 保釈保証金、供託金の還付、和解金等弁済受領、依頼者からの預り金の禁止
⑤ ①、②の場合、新しく受任する弁護士等に誠実に引き継ぎをしなければならない。
⑥ 弁護士報酬の和解金等から相殺禁止
⑦ 新たに復代理人、他の弁護士等の雇用の禁止
⑧ 処分を受ける前に選任した復代理人、雇用する弁護士等に対する指示及び監督の禁止
⑨ 法律事務所の管理、賃貸借契約、雇用する弁護士等、従業員との雇用契約の継続は可能
⑩ 法律事務所を自らの弁護士業務を行う目的で使用することの禁止(受任事件の引継その他この基準によって業務停止期間中も認められている事務等のため必要なときは、使用目的等必要な事項の届出を行った上で、弁護士会の承認を得て法律事務所を使用することができる。)
⑪ 弁護士及び法律事務所であることを表示する表札、看板の除去。ただし、業務停止処分中であること及びその期間を弁護士会の指示する方法で表示することに代えることができる
⑫ 広告の除去
⑬ 弁護士の肩書又は法律事務所名を表示した名刺、事務用箋、封筒使用の禁止
⑭ 弁護士記章、身分証明書の返還
⑮ 会務活動の禁止
⑯ 公務等の辞任
⑰ 弁護士又は弁護士となる資格を有する者として弁理士、税理士その他の資格の業務禁止
⑱ 戸籍謄本等請求用紙の返還
⑲ 弁護士会等との連絡
退会命令
対象弁護士をその所属弁護士会から一方的に退会させる処分です。告知の日からその所属弁護士会を当然に退会し弁護士の身分を失うことになります。
執行停止、効力停止がなされない限り弁護士ではなくなるから、当然、弁護士や法律事務所の表示はしてはならないし、利益を得る目的で法律相談その他法律事務を行うことはできません。
ただちに事務所を閉鎖しなければなりませんし、名刺を使用してはならず、看板等も除去しなければなりません。記章や身分証明書も返還しなければなりません。弁護士ではなくなるため、弁護士会は指導監督をすることはできなくなります。したがって、退会命令後の業務に対しては、基本的には刑罰の対象として対応することになります(法77条)。
退会命令の処分が告知された後は会費の徴収はされませんが、効力停止期間中の会費は徴収されます。
もっとも、弁護士の身分を失わせるだけで、弁護士となる資格を失わせるものではないから、法律上は、あらたに弁護士会に対して登録請求をすることは可能です。しかしながら、過去の退会命令の懲戒処分を前提に入会審査が行われることから、登録拒絶の可能性は極めて高くなります(法12条1項、15条1項)。
除名
対象弁護士の弁護士たる身分を一方的に奪う処分です。告知の日から3年間、弁護士となる資格を失うことになります。したがって、この期間は再登録の請求はできなくなります。
弁護士でなくなることに伴う効果は、退会命令と同様です。
告知の日から3年経過後は再登録の請求は可能になりますが、これが認められた件は過去に1件だけです。
弁理士及び税理士業務への影響
弁護士法3条2項は、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」と規定しています。他方、弁理士法7条2項、税理士法3条1項3号において、弁護士となる資格を有する者に、弁理士や税理士となる資格を認めています。
業務停止以上の懲戒処分がされた場合に、これらの業務にいかなる影響があるかを検討します。
弁理士、税理士登録なくこれらの事務を行っていた者
弁護士が、登録なく弁理士業、税理士業(通知税理士)を行っていた場合、これらはあくまで弁護士法に基づく弁護士としての業務としてこれらの事務を行う者に過ぎないため、業務停止以上の処分の効果として、これらの事務は当然に禁止されることになります。
弁護士資格に基づき弁理士や税理士の登録をしてこれら業務を行っていた者
この場合、税理士法には、弁護士の業務停止期間中税理士業務を行ってはならない規定(税理士法43条)、懲戒処分により除名された場合の登録抹消(同法4条9号、26条1項4号)が定められています(退会命令の場合、明示的な規定は見当たりません。)。
他方、弁理士法には、懲戒処分により除名された場合の登録の抹消(弁理士法8条7号、24条1項3号)の規定しかありません。もっとも、日弁連の弁護士会に対する指導連絡監督権を根拠に「被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会のとるべき措置に関する基準」によって、業務停止期間中の弁理士業務は禁止されています。
懲戒処分の種類(弁護士法人)
戒告
弁護士に対するそれと異なる点はありません。
2年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止
主たる法律事務所所在地の弁護士会は、弁護士法人全体に対する指導監督権を有していることから、弁護士法人全部又は一部の法律事務所に対する業務の停止を命ずることができます。つまり、主たる法律事務所所在地でない地域の法律事務所のみの処分も可能です。
対して従たる法律事務所所在地の弁護士会は、その地域内にある法律事務所(複数ある場合はそのうちの全部もしくは一部)の処分のみが可能です。
なお、弁護士法人に対する業務停止は、当然にその社員弁護士や使用人弁護士に及ぶものではなく、個人としての業務継続は可能です。
その他、弁護士法人が業務停止となった場合の取るべき措置については次のとおりです。
被懲戒弁護士法人の業務停止期間中における業務規制等について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準(外部リンク)
退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。)
退会命令の処分を行うことができるのは、当該地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限ります。
つまり、主たる法律事務所がある地域の弁護士会は、退会命令を選択できないことになります。
除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。)
退会命令とは逆に、除名処分をできるのは主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限ります。
この場合、弁護士法人は当然に解散となり、清算手続きに入ります。この清算手続き中は弁護士会の監督が必要であることから、清算結了までの間、法人の弁護士会会員たる身分は存続するとされています。
日弁連の懲戒手続
日弁連の懲戒委員手続に関する機関
日弁連の綱紀委員会
日弁連の綱紀委員会は、平成15年弁護士法改正によって初めて法定されました。同年以前も存在はしていましたが、法律上の根拠はありませんでした。
弁護士である委員24人、裁判官、検察官及び学識経験者各2名により構成され、さらに予備委員がいます。
日弁連の綱紀委員会の任務は次の4つです。
①日弁連が懲戒手続に付した懲戒事案の調査(弁護士法60条2項)
②綱紀審査会から嘱託を受けた事項の調査(弁護士法71条の6第2項)
③弁護士会の議決に基づく懲戒しない旨の決定及び弁護士会がその綱紀委員会の調査の段階で相当の期間内に懲戒の手続を追えないことに対する異議の審査(弁護士法64条の2第1項、2項、4項、5項)
④その他弁護士及び弁護士法人の綱紀保持に関する事項(弁護士法70条3項、会則70条2項)
綱紀審査会
綱紀審査会は、国民の意見を反映させて懲戒手続の適正を確保する観点から、平成15年の弁護士法改正により設置されることになった機関です。
すなわち、弁護士自治の観点から、綱紀審査会を日弁連の外部組織ではなく内部組織として置いたものです。
学識経験者11名により構成され、この中に、弁護士、裁判官、検察官、またはこれらであった者は含まれません(弁護士法71条の2、71条の3第1項)。
綱紀審査会の任務は、日弁連が異議の申出を却下し又は棄却する決定をした場合において、不服があるときに行う綱紀審査の申出(弁護士法71条2項、64条の3)の審査です。
日弁連の懲戒委員会
日弁連の懲戒委員会は、弁護士である委員8人、裁判官、検察官である委員各2人、学識経験者である委員3人により構成され、さらに予備委員がいます。
日弁連の懲戒委員会の任務は、
①弁護士法59条の審査請求があったとき
②弁護士会の懲戒委員会の審査に付された事案について弁護士法64条1項の規定による異議の申出があったとき
③日弁連の綱紀委員会が弁護士法60条3項の規定により懲戒委員会に事案の審査を求めることが相当と認める旨を議決したとき
にそれぞれ必要な審査をすることです。
異議の申出
異議の申出の種類
懲戒請求者は、弁護士法第58条第1項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があったにもかかわらず、
①弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき
②相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき(相当期間異議)
③弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するとき
には、異議の申出をすることができます(弁護士法64条1項)。
この場合、弁護士会の綱紀委員会の議決に対しては日弁連の綱紀委員会に、弁護士会の懲戒委員会の議決に対しては日弁連の懲戒委員会にそれぞれ審査が付されることになります。
異議の申出権者
異議の申出をなしうるのは、懲戒請求をした者に限られています。
懲戒請求を取り下げた者は異議の申出もできないと解されており、懲戒請求者が死亡した場合の相続人も異議の申出をすることができません。
取下げの効果
異議の申出の取下げはいつでもすることができ(日弁連綱紀委員会規程46条1項、2項、日弁連懲戒委員会規程73条1項、2項)、異議の申出の取下げがあったときは審査を終了する旨の議決がなされます(日弁連綱紀委員会規程46条3項、日弁連懲戒委員会規程73条3項)。
申出期間
異議の申出期間は、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です。
審査について
弁護士会の綱紀委員会の議決に対しては日弁連の綱紀委員会に、弁護士会の懲戒委員会の議決に対しては日弁連の懲戒委員会にそれぞれ審査が付されることになります。
「懲戒処分が不当に軽いと思料するとき」を理由とする異議の申出は必ず日弁連の懲戒委員会の審査となります。
「相当の期間内に懲戒の手続を終えないとき」を理由とする異議の申出は、綱紀委員会、懲戒委員会いずれもあり得ます。「相当の期間」がどの程度をいうかは一義的に明確ではありませんが、綱紀委員会の調査、懲戒委員会の審査はいずれも原則的な審理期間を6か月と定めており、例外的に「事案が複雑なときその他特別の事情があるときは、この限りでない」としています(日弁連綱紀委員会規程28条、52条、日弁連懲戒委員会規程38条、52条、68条)。
審査の対象は、原弁護士会の決定の当否(相当期間異議を除く)であり、決定の当否の基準時は原弁護士会の決定がなされた時点であると解されています。
議決の種類
各議決の種類は次のとおりです。
綱紀委員会における異議の申出に対する議決
① 「●●弁護士会の懲戒委員会の審査を求めることを相当と認める。」
② 「異議の申出に理由があると認める。●●弁護士会は、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をせよ。」(相当期間異議の場合)
③ 「本件異議申出を却下することを相当と認める。」「本件異議申出を棄却することを相当と認める。」
④ 「本懲戒手続は、(対象弁護士の死亡/弁護士資格の喪失/異議の申出の取下げ)により終了した。」
懲戒委員会における異議の申出に対する議決
① 「●●弁護士会が令和●●年●月●日付けでなした対象弁護士等を懲戒しない旨の決定を取り消す。対象弁護士等を戒告することを相当と認める。」
② 「異議の申出に理由があると認める。●●弁護士会は、速やかに懲戒の手続を進め、対象弁護士等を懲戒し、又は懲戒しない旨の決定をせよ。」(相当期間異議の場合)
③ 「●●弁護士会が令和●●年●月●日付けでなした対象弁護士等に対する懲戒処分を次のとおり変更することを相当と認める。対象弁護士等に対し●月間弁護士の業務を停止する。」
④ 「本件異議申出を却下することを相当と認める。」「本件異議申出を棄却することを相当と認める。」
⑤ 「本懲戒手続は、(対象弁護士の死亡/弁護士資格の喪失/異議の申出の取下げ)により終了した。」
原弁護士会への差し戻しの可否
日弁連の懲戒委員会は、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたこと又は弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料することを理由とする異議の申出に対して、理由があると認めるときは、日弁連自らが懲戒することになります。
したがって、原弁護士会の懲戒委員会に対して差し戻して審査をさせることはありません。
弁護士法62条の制限について
異議の申出がなされると、再び弁護士法62条の制限(登録換え、登録取消の制限)を受けることになります。
したがって、原弁護士会の懲戒処分の告知、または不処分の通知があった後は、弁護士法62条の制限はなくなるものの、その後の異議の申出によって再び制限を受けることになるため、タイムラグが生じる結果となります。
異議の申出が認められた場合の懲戒処分の効果
異議の申出が認められた場合、原弁護士会の懲戒処分は取り消され、日弁連の処分が効力を持つことになります。
ただし、業務停止処分をより長期とした場合、既に停止された期間は日弁連の業務停止期間に算入されます。
日弁連の決定に対する不服申立て
対象弁護士の不服
異議の申出により対象弁護士が懲戒された、又はより重い処分になった場合は、弁護士法60条により日弁連から懲戒されたことになるので、弁護士法61条により東京高等裁判所に対して取消の訴えをすることが可能です。
審査請求ではないことに注意が必要です。
異議申出人の不服
日弁連の綱紀委員会の議決によって異議の申出が却下ないし棄却されたときは、異議申出人は綱紀委員会による綱紀審査の申出をすることができます。
他方、日弁連の懲戒委員会の議決によって異議の申出が却下ないし棄却されたときには、裁判所等へ不服申立てをする手段はありません。
綱紀審査会による綱紀審査
綱紀審査の申出
綱紀審査の申出は、弁護士会が、その綱紀委員会が懲戒委員会に審査を求めないことを相当する議決に基づき懲戒しない旨の決定に対し、懲戒請求者から異議の申出があり、さらに日弁連がその綱紀委員会の議決に基づき異議の申出を却下又は棄却する決定をしたことに対して、懲戒請求者がなお不服がある場合の不服申立て手段です(弁護士法64条の3)。
したがって、弁護士会が懲戒委員会に事案の審査を求めた場合には、その結論がどうであれ、綱紀審査の申出はできないことになります。
綱紀審査申出人
綱紀審査の申出ができる者は、異議の申出を却下又は棄却された者に限られます。
異議申出人が死亡した後の相続人や、異議の申出を取り下げた者も綱紀審査の申出をすることはできません。
取下げの効果
綱紀審査の申出の取下げについては、異議の申出の取下げと同様、審査終了の効果を生じます。
綱紀審査の申出期間
綱紀審査の申出は、通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければなりません。
綱紀審査の対象と判断の基準時
綱紀審査の対象は、弁護士会の綱紀委員会の議決の当否であり、基準時は同議決に基づく決定がなされた時点です。
綱紀審査会の審査
綱紀審査会は、綱紀審査に関し必要があるときは、対象弁護士の所属弁護士会の綱紀委員会、又は日弁連の綱紀委員会に必要な調査を嘱託することもできますが(弁護士法71条の6第2項)、審査不十分として日弁連や弁護士会に差し戻す権限まではありません。
綱紀審査会の制度が、懲戒請求事由を一から調べ直して判断するというものではなく、弁護士会及び日弁連の綱紀委員会の2度にわたる判断を市民の目から見直すというものであり、あくまでも補充的な調査権限を与えたものに過ぎないからです。
弁護士法62条の制限について
綱紀審査の申出がなされ、綱紀審査会に事案が係属すると、再び弁護士法62条により登録換え、登録取消が制限されることになります。
議決の種類
綱紀審査会の議決の種類は次のとおりです(綱紀審査規程28条)。
①原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める旨の議決。
②綱紀審査の申出が不適法として却下することを相当と認める旨の議決。
③原弁護士会の懲戒委員会に事案の審査を求める旨の議決が得られなかった旨の議決。
④ 対象弁護士が死亡したとき、又は弁護士でなくなったときは、審査を終了する旨の議決。
⑤綱紀審査の申出の取下げがあったことを理由として審査を終了する旨の議決(綱紀審査規程29条3項)。
不服申立て
綱紀審査会の議決に基づく日弁連の決定に対して不服申立ての制度は設けられていません。
したがって、これにより手続が終了する決定をした場合、懲戒手続は終了することになります。
審査請求
審査請求の意義
弁護士法は懲戒に関し、弁護士会を行政庁に準じて考え、その不服申立ての具体的手続等について行政不服審査法が適用されることとしています(日弁連調査室・条解弁護士法<第5版>498頁)。
弁護士法59条1項は、懲戒を受けた弁護士等の不服申立て手段を審査請求であると定めています。
平成26年の行政不服審査法の改正によって弁護士法59条2項3項が新設され、2項が一部適用除外を、3項が日弁連の手続にあわせた読み替えを定めています。
審査請求人
審査請求人たり得るのは、弁護士会により懲戒処分を受けた弁護士又は弁護士法人です。
弁護士の死亡後に関しては、行政不服審査法上は審査請求の承継が認められるものの(行政不服審査法15条)、弁護士の懲戒処分が弁護士としての地位・資格に関する一身専属的なものであることから、審査手続の承継はあり得ず、死亡した時点で当然に審査手続は終了するものと解されています。
審査請求の方式
審査請求をするには、原弁護士会又は日弁連に対して、審査請求書正本1通及び副本2通を提出しなければなりません(日弁連懲戒委員会規程34条1項)。
また、弁護士法人の場合は登記事項証明書を添える必要があります。
審査請求書には、必要的記載事項として、行政不服審査法19条2項各号の事項、すなわち、
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分(当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定)があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
及び、審査請求期間の経過後において審査請求する場合は、正当な理由を記載する必要があり(同法19条5項3号)、これに加えて、
所属弁護士会の名称
も記載しなければなりません。
審査請求の期間
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行う必要があります(行政不服審査法18条1項)。
同期間内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過すれば原則として審査請求することはできません(同2項)。
なお、郵送で提出した場合、郵送に要した日数は上記期間に算入されません(同3項)。
また、期間の末日が行政機関の休日にあたるときは、行政機関の休日の翌日が当該期間の末日とみなされます(懲戒委員会規程34条の2)。
実質的審理
審査請求の実質的審理は日弁連の懲戒委員会で行われ、審査請求により裁決するには、懲戒委員会の議決に基づかなければなりません。
具体的な審査手続については日弁連の懲戒委員会及び懲戒手続に関する規程(懲戒委員会規程)に定められていますが、同規程によれば、懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは職権で関係人を審尋し(39条1項)、書類その他の物件の所持人にその物件の提出を求め(26条)、学識経験のある者に鑑定を嘱託し(27条)、検証することができる(28条)とされています。
審査は、弁護士会の処分の違法(弁護士会の裁量の逸脱、裁量権の濫用)に限らず、処分の当不当についても及びます。
審査の対象である事実は、審査請求にかかる事実、すなわち弁護士会が懲戒処分をした根拠となった当該弁護士等の非行事実の範囲に限られ、その範囲外のことを審査することはできません。
判断の基準時
審査請求の対象とされる処分の適否を判断する場合、その基準時は弁護士会の処分時と解されています。
効力停止
弁護士等の懲戒処分については告知によりその効力を発生するため、審査請求を申し立てただけでは処分の効力は停止しません(行政不服審査法25条1項)。
そこで、行政不服審査法25条2項は執行停止の申立権を与え、日弁連の懲戒委員会規程46条は「懲戒処分の効力停止」を規定しています。
ただし、効力停止の申立ては、審査請求が要件になっているため、効力停止の申立てを先行したり、効力停止の申立てを単独で行ったりすることはできません。
日弁連は、必要があると認めるときは、審査請求人の請求又は職権により、懲戒処分の効力を停止することができます(同条1項)。
効力停止の申立てに当たっては、効力停止申立書正本1通を日弁連に提出することになります(同条2項)。
日弁連は、いったん効力停止を認めたとしても、事情の変更によりこの効力停止の決定を取り消すことができます(同条3項)。
また、審査請求、又は効力停止の申立てが取り下げられたときは、効力停止の決定も取り消されます(同条4項)。
効力停止の決定に遡及効はありませんが、形成的効力をもつ懲戒処分の効力を停止させて、その後は処分がなかったことと同様の効果を与えることになります。
効力停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときに限って認められます。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は審査請求について理由がないとみえるときは、この限りではありません(行政不服審査法25条3項)。
効力停止の判断に関しては、懲戒委員会の議決に基づかず、日弁連が行うことになります。ただし、効力を停止するとき、効力停止の申立てを却下するとき、いったんした効力停止の決定を取り消すときはあらかじめ懲戒委員会の意見を聴かなければなりません。
なお、日弁連の効力停止の決定に対する不服申立ては認められていません。
懲戒委員会の審査請求に対する議決
懲戒委員会がする審査請求の議決の種類は次のとおりです。
①本件審査請求を却下する。(審査請求が不適法の場合)
②本件は、被審査人の死亡により終了した。(審査請求人が死亡した場合)
③本件審査請求を棄却する。(本案について審査の結果、審査請求に理由がないとして、原弁護士会の処分を是認する場合)
④「●●弁護士会が○○年○○月○○日付けでなした審査請求人に対する懲戒処分を取り消す。審査請求人を懲戒しない」「●●弁護士会が○○年○○月○○日付けでなした審査請求人に対する懲戒処分を次のとおり変更する。審査請求人を(戒告)する」(審査請求に理由があることを認めて、原弁護士会の処分を取り消したり、変更する場合。ただし不利益変更はできない。)
裁決
日弁連は、懲戒委員会の議決に基づき、裁決を行うことになります。
取消し、又は変更がなされた場合、原弁護士会の処分はなくなり、日弁連の処分が適用になります。
より短期の業務停止になった場合には、弁護士会の処分により業務が行えなかった期間は日弁連の業務停止処分における期間に算入されます。
なお、審査請求が却下、棄却または変更された場合には、東京高等裁判所に対する取消の訴え以外に救済の手段はありません。